いすみ市農業委員会
農業委員会の業務
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政委員会です。主な業務としては、農業生産の基盤となる優良農地を守り有効活用するための取り組みで、法令に基づく必須業務や任意の業務、市長等への建議や農業者の相談活動などを行っています。
農地法の規定に基づく許可について
農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は農地法第3条の許可が必要です。
自らが所有する農地を農地以外の用途に転用したい時、例えば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに使用したい場合は、農地法第4条の許可が必要です。
農地転用を伴う所有権移転や賃貸借権の設定をする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
許可申請の受付期間について
農地法の許可が必要な方は、毎月21日~25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)までの受付期間内に申請書を農業委員会へ提出して下さい。
農業委員会総会について
農業委員会では毎月8日前後(予定)に農業委員会総会を開催し、許可申請内容を審議しております。
総会議事録
農地法第3条許可申請について
農地を耕作目的で所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可基準
農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
- 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)
下限面積について
令和5年4月1日より農地法改正に伴い、耕作目的での権利取得(所有権・賃借権・使用貸借権等)をするための許可要件である耕作面積の下限が撤廃となりました。
農地法第3条許可申請に必要な書類(詳しくは農地法3条関係事務指針より)
農地法3条関係事務指針 (Wordファイル: 474.5KB)
農地法第3条許可申請に必要な書類書類一覧
相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。
農地法第4、5条許可申請について
農地を農地以外の用途に転用したい時、例えば農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに使用したい場合には事前に許可等が必要です。
農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可を、農地の所有者以外の者が、その所有者から買ったり借りたりして転用を行う場合は、農地法第5条の許可が必要となります。申請書及び添付書類については、千葉県農林水産部農地課の農地転用関係事務指針より、本文(添付書類)及び様式をダウンロードしてください。
農地転用関係事務指針についてに記載されている様式以外で添付が必要な書類で、資金計画書、確約書(資材置場、駐車場等が転用目的の場合添付)については、こちらを参考にして下さい。
資金計画書・確約書のダウンロード
買受適格証明書願について
民事執行法による売却又は国税徴収法の滞納処分による公売により、農地法の許可を要する農地等を取得する場合には、次のような手続きが必要になります。
買受適格証明
競売(公売)により農地等を取得するため買受の申し出をすることができる者は、知事又は農業委員会の交付した買受適格証明書を有する者に限定されていることから、競売(公売)に参加しようとする者は「買受適格証明願」を該当土地の所在する市町村農業委員会へ提出し、証明書の交付を受けてください。
1.買受適格証明願申請書に必要な書類(耕作を目的とする場合)
その他
最高価買受申出人となった者は、落札後農地法第3条の許可申請を行ってください。添付書類は、競落調書の添付をお願いいたします。
また、農地法第3条許可申請書の添付書類に準ずる書類も添付になりますが、買受証明願の申請時と内容が同じ場合には申請書の末尾にその旨を記載して添付することを省略することが出来ます。
2.競売(公売)売買受適格証明願申請書に必要な書類(転用を目的とする場合)
競売・公売事件の公告の原本又は写し、そして農地法第5条の規定による許可申請手続きの添付書類に準ずる書類。
申請書及び添付書類については、農地転用関係事務指針より、本文(添付書類)及び様式をダウンロードしてください。
最高価買受申出人となった者は、落札後農地法第5条の許可申請を行ってください。添付書類は、競落調書の添付をお願いいたします。
備考
また、農地法第5条許可申請書の添付書類に準ずる書類も添付になりますが、買受証明願の申請時と内容が同じ場合には申請書の末尾にその旨を記載して添付することを省略することが出来ます。
農地法第3条許可申請書の提出部数については原本を1部提出して下さい。
また、農地法第4、5条許可申請書については、原本及び副本を各1部の提出となります。
なお、郵送での受付は出来ませんので、申請人(譲受人及び譲渡人)が直接窓口に提出をお願いいたします。なお、申請書の提出及び作成等を代理人が行う場合には、委任状が必要となります。
軽微な農地改良の届出書について
農地所有者自らが従前の作土と同等以上の土砂を用いて農地の改善を行う場合には、事業実施の1か月前までに軽微な農地改良の届出書の提出をお願いいたします。
届出の要件
次の要件を全て満たす場合は軽微な農地改良として取り扱います。それ以外のものについては、一時転用許可が必要な農地造成行為になります。
1.平均盛土厚さが1m未満であること。
2.他法令(条例を含む)の許認可等を要するものでないこと。
3.工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間が3か月以内であること。
軽微な農地改良の届出書(様式第16号 農地転用関係事務指針よりダウンロード)
| 書類の種類 | 備考 |
|---|---|
| 土地の登記事項証明書 | 全部事項証明書に限る。千葉地方法務局いすみ出張所より取得してください。 |
| 公図の写し | 千葉地方法務局いすみ出張所またはいすみ市税務課より取得してください。周辺土地の地目、面積、所有者等の記入をお願いいたします。 |
| 案内図 | 申請地の案内図(住宅地図等) |
| 埋立事業計画書 | 様式第20号(農地転用関係事務指針よりダウンロード) |
| 埋立事業計画図 | 平面及び断面図 |
| 土地改良区の同意書 | 土地改良区施行区域内の場合には添付をお願いいたします。 |
| 承諾書 | 隣接農地耕作者より承諾書(Wordファイル:28KB)の添付をお願いいたします。 |
| 軽微な農地改良の届出書に係る同意書 | 申請地区の担当農業委員より同意書(Wordファイル:32.5KB)の添付をお願いいたします。 |
| 誓約書 | 所有者は畑として耕作する、施工者は産業廃棄物等を混入しない旨が記載された誓約書(Wordファイル:29.5KB)の添付をお願いいたします。 |
注意
証明書類は、申請前3か月以内のものの添付をお願いいたします。その他、必要に応じて書類の添付をお願いする場合があります。
農業者年金
農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的をも併せ持つ制度です。
(1)少子高齢化時代に強い年金です
自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。
(2)農業に従事する人は広く加入できます
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受けられます。
旧制度の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
(3)保険料の額は自由に決められます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料が決められます(月額2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
(4)80歳までの保証が付いた終身年金です
年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受けられるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。
(5)認定農業者など担い手には、保険料の国庫助成があります
認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助(政策支援)があり、基本保険料2万円のうち最高半額、生涯で最大216万円の補助を受けることができます。国庫補助額とその運用益は個人ごとに積み立てられ、将来受給する特例付加年金の原資となります。
特例付加年金を受給するためには農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。
自分の保険料で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することができます。このため、65歳からは農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、体力に応じて特例付加年金の受給の時期を決めることもできます。
詳細については、農業者年金基金ホームページをご覧ください
(6)税制面でも特例が用意されています
支払った保険料(最高年額80万4千円)は全額、社会保険料控除の対象になり(民間の個人年金の場合、控除額の上限は5万円です)、保険料の15%~30%程度という大きな節税効果があります。
また、農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する運用益は課税されません。将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用されます。
詳細については、農業者年金基金ホームページをご覧ください
令和7年度標準農作業賃金及び機械による標準農作業料金
金額については、標準的な目安となるものであり、湿田・圃場の大小及び地形等によって、若干の格差がありますので、参考としてご活用ください。
令和7年度標準農作業料金 (PDFファイル: 98.4KB)
農地賃借料情報提供について
令和2年1月から令和2年12月までに締結(公告)された、農地の賃借料水準(10アール当たり)を公表します。
この「賃借料情報」は、実勢の集計地であり、賃借料決定の参考として提供するものでありますので、実際の契約の締結の際には貸し手と借り手の両者で協議したうえで締結してください。
農地利用状況調査について
いすみ市農業委員会では、7月から9月にかけて遊休農地の実態把握と発生防止、違反転用の防止や早期発見を目的として、市内農地の利用状況について調査を実施します。
このため、農業委員・農地利用最適化推進委員や調査員などが農地を見回り、耕作放棄されている農地へ立ちいることや、お話しを伺うこともありますのでご理解、ご協力をお願いします。
農地等の利用の最適化の推進について
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項に基づき公表します。
農業委員会等に関する法律第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況、農業委員会における事務の実施状況を公表するに当たり、最適化活動の目標を設定しました。
令和7年度最適化活動の目標の設定等 (PDFファイル: 231.2KB)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 (PDFファイル: 186.8KB)
農地銀行制度
農地銀行とは
耕作又は管理できなくなった農地を貸したい又は売りたい希望を持つ方にその農地を「農地銀行」に登録していただき、その登録された情報を農地を借りたい又は買いたい希望を持つ方(新規就農希望の方や経営規模を拡大したい農業者の方)へ情報提供し、農地の貸借・売買を支援する制度です。
登録及びあっせんについて
別紙様式に必要事項を記入の上、農業委員会事務局へ申請してください。
農地を貸したい又は売りたい希望者
農地銀行登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.3KB)
農地銀行登録抹消届(様式第2号) (Wordファイル: 15.0KB)
農地を借りたい又は買いたい希望者
登録農地情報提供申請書(様式第3号) (Wordファイル: 15.3KB)
農地あっせん希望申請書(様式第4号) (Wordファイル: 15.7KB)
農地あっせん希望申請書(様式第4号別紙) (Wordファイル: 16.3KB)
登録されている農地について
登録されている農地を一覧表にしてあります。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
登録農地一覧(夷隅地域) (PDFファイル: 321.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





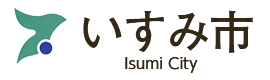
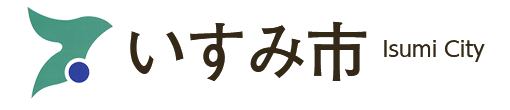





更新日:2023年04月01日