認知症施策の推進
世界アルツハイマーデー
毎年9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。
アルツハイマー病等に関する認識を高め、世界の患者と家族に希望をもたらすことを目的としています。あわせて、9月は「世界アルツハイマー月間」となっています。

(出典:公益社団法人認知症の人と家族の会)
認知症の日
2024年1月に施行された認知症基本法により、9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定め、認知症の啓発のため様々な取り組みを行うこととなりました。
1.市内にお住まいの認知症の方々の作品等の展示
☆いすみ市役所 大原庁舎
令和7年9月に市役所の正面玄関に、いすみ市内のグループホーム入居者の方の作品を展示しました。また、認知症を患っている方(漫画家)が増田明美氏の似顔絵を描いてくださいました。

正面玄関全体

清常雄氏作品

グループホームいきいきの家いすみ 作品

グループホームいきいきの家岬 作品

グループホームたけんこ 作品

グループホーム咲の樹 作品

グループホーム咲の樹 作品

グループホーム菜の花 作品

グループホーム菜の花 作品
2.認知症シンポジウム2025
夷隅郡市地域包括支援センター連絡会では、認知症に対する理解を深め、夷隅郡市の地域全体で認知症の方やその家族を支えるための地域づくりを目的に、下記のとおり認知症シンポジウムを開催しました。
【日時】令和7年9月20日(土曜日)14:00~16:00(開場13:30)
【会場】勝浦市芸術文化センター・キュステ (勝浦市沢倉523-1)
【内容】第1部 インタビュー形式による本人発信
「私の暮らし方、医療や介護に望むこと」
発信者:夷隅郡市認知症大使
第2部 特別講演(質疑応答含)
「脳の健康と向き合う ~認知症の治療とケアの新たな展開~」
講師:認知症専門医 野村 浩一 氏
医学博士、医療法人SHIODA 塩田病院 副院長、
一般社団法人 夷隅医師会 副会長、一般社団法人 老人病研究会 理事
認知症シンポジウム2025チラシ (PDFファイル: 2.6MB)
いすみ市での取り組み
認知症の方やそのご家族の交流会
認知症の方やその家族が気軽に参加し、日頃の様子や不安などを語り合い、情報を共有し、介護の疑問を聞いたりすることで、心の負担を軽くするための交流会です。
「公益社団法人認知症の人と家族の会」による個別相談も行います。
家族の会とは・・
認知症になっても安心して暮らせる社会、認知症とともに生きる社会づくりをめざし、認知症の人や介護家族が中心になって活動している全国組織です。
対象:認知症の方や認知症の方の介護をするご家族
日時:令和8年2月19日(木曜日) 13:30~15:30
場所:岬公民館 第6研修室(いすみ市岬町長者22)
参加費:無料
※事前のお申込みをお願いいたします。
認知症サポーター養成講座

認知症サポーター養成講座 いすみ市役所大原庁舎にて
認知症を正しく理解し、認知症に対する誤解と偏見を解消し、認知症の人や家族が安心して暮らせるまちをみんなで作っていき、見守り応援する「認知症サポーター」になるための講座を開催しています。
詳しくは下記をご覧ください。
いすみオレンジネットワーク
いすみオレンジネットワークとは、認知症サポーターステップアップ講座を受講した方が中心となり、認知症の人や家族が安心して暮らし続けられる地域づくりを推進しています。
徘徊模擬訓練
徘徊模擬訓練とは、認知症の人が道に迷って帰れないなどして行方不明になった場合を想定し、地域住民が認知症高齢者を見つける、声をかける、保護するなどの訓練を行うものです。
令和7年度も徘徊模擬訓練を下記のとおり実施予定です。
日時:令和7年11月3日(月・祝)
時間:第10回いすみふるさとまつり開催時間中に実施
場所:岬運動場(いすみ市岬町長者2-3)
その他:参加費無料。事前申し込み不要。
誰でもお気軽にご参加ください。
過去の活動実績

◎令和5年度のいすみ市徘徊模擬訓練の様子
いすみオレンジネットワーク参加者が中心となり、市内のホームセンターに協力を得て試験的に実施しました。
◎令和6年度の活動の様子
令和6年11月3日に「いすみふるさとまつり」が開催されました。その一画にいすみオレンジネットワークのブースを設け認知症の啓発を行いました。
また、会場で10時から12時まで徘徊模擬訓練を実施し、子供から大人まで100人以上の方に参加していただきました!

ブースではオレンジネットワーク、認知症に関するチラシを配布しました

徘徊模擬訓練参加者を募りました

徘徊している認知症の方を見つけて声を掛けました

オレンジネットワークのメンバーが認知症役となり会場を歩きました
認知症初期集中支援チーム
認知症になっても本人の意思が尊重され、安心して暮らし続けられるよう、認知症サポート医(大多喜病院医師)と専門知職を持つ保健師、社会福祉士、介護福祉士等で構成された支援チームが、認知症の方(疑いのある方)やそのご家族を訪問し相談に応じるものです。病院受診やサービス利用、家族への支援などの初期支援を包括的に・集中的に行います。
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になり、一人で決めることが心配な人たちは、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を一人で行うことが難しい場合があります。成年後見制度は、このような人たちを法的に保護するための制度であり、成年後見制度の利用促進を含めた総合的な権利擁護支援、意思決定支援の取り組みが進められています。
いすみ市では認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で65歳以上の方の成年後見制度の利用について、以下の3項目で支援します。
1.市長が行う審判の申し立て
2.審判の申し立てに要する費用の助成
3.審判に基づき家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人に対する報酬の助成
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





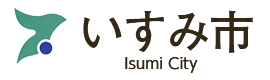
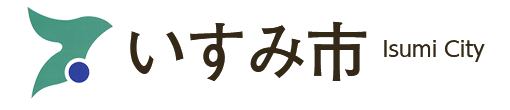





更新日:2023年09月01日