個人市県民税(住民税)額の計算
- 収入金額-必要経費等=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-調整控除-税額控除等=所得割額
- 所得割額+均等割額=個人市県民税(住民税)額
(注意)退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、他の所得と区分して税額計算をします。
(1)所得金額
- 所得金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費等を差し引いたものです。
- 所得の種類は、所得税と同様の10種類に区分され、それぞれの計算方法により算出します。
所得の種類と所得金額の計算方法
1 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子)
収入金額=利子所得の金額
2 配当所得(株式や出資の配当など)
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得(地代、家賃など)
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得(給料、賃金、賞与など)
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
| 収入金額(A) | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| ~550,999 | 0 | |
| 551,000~1,618,999 | A-550,000 | |
| 1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | |
| 1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | |
| 1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | |
| 1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | |
| 1,628,000~1,799,999 |
A÷4=B(注意)千円未満切捨て |
|
| 1,800,000~3,599,999 | A÷4=B(注意)千円未満切捨て B×2.8-80,000 |
|
| 3,600,000~6,599,999 | A÷4=B(注意)千円未満切捨て B×3.2-440,000 |
|
| 6,600,000~8,499,999 | A×0.9-1,100,000 | |
| 8,500,000~ | A-1,950,000 | |
特定支出の控除の特例について
給与所得者が、通勤費や出張等の旅費などに支出(特定支出)し、その年の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分について、確定申告により給与所得の金額の計算上控除することができます。
6 退職所得(退職金、退職手当など)
特定役員退職手当等
収入金額-退職所得控除額=退職所得の金額
特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
(1)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
- 国会議員や地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員や地方公務員
(2)「役員等勤続年数」とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間(以下「役員等勤続期間」といいます。)の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
特定役員退職手当等以外
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得控除額の計算
勤務年数が20年以下
勤続年数×40万円=退職所得控除額(80万円未満の場合には80万円)
勤務年数が20年超
(勤続年数-20年)×70万円+800万円=退職所得控除額
7 山林所得(山林の立木を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得(生命保険等の一時金、満期返戻金、懸賞当選金など)
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得(公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得)
次の1.と2.の合計額=雑所得の金額
- 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
- 1.を除く雑所得の収入金額-必要経費
|
年齢(前年12月31日現在) |
公的年金等の収入金額(A) | 雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
| 65歳未満 | 130万円未満 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
| 130万円以上~410万円未満 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
| 410万円以上~770万円未満 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
| 770万円以上~1,000万円未満 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
| 1,000万円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 | |
| 65歳以上 | 330万円以下 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
| 330万円以上~410万円未満 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
| 410万円以上~770万円未満 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
| 770万円以上~1,000万円未満 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
| 1,000万円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 | |
非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区分され、課税の対象にはなりません。
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(障害年金、遺族年金)など
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当
- 損害保険料、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
(2)課税所得金額
課税所得金額とは、所得金額からそれぞれの所得控除の合計額を差し引いて千円未満の額を切り捨てたものです。
| 種類 | 控除額 |
|---|---|
| 雑損控除 | 次のいずれか多い額
|
| 医療費控除 |
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれかの制度を選択することができます。(申告後に制度の選択を変更することはできません。) 従来の医療費控除額の計算式(原則)総所得金額等に応じ、以下の計算方法により算出(限度額200万円)
セルフメディケーション税制の計算式(特例)(特定一般用医薬品の購入対価-保険等により補てんされた額)-12,000円(限度額88,000円) |
| 社会保険料控除 | 支払った額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 |
| 生命保険料控除 |
旧契約(平成23年12月31日以前に契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合生命保険料及び個人年金保険料の両方を支払った場合は、支払った保険料の金額に応じ、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(それぞれ最高35,000円、2つ合計で最高70,000円)
新契約(平成24年1月1日以後に契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合各種にわたり支払った場合は、支払った保険料の金額に応じ以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(それぞれ最高28,000円、3つ合計で最高70,000円)
生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払った場合新契約・旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(それぞれ最高28,000円、合計で最高70,000円) |
|
地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円) (経過措置) 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、支払った保険料の額に応じ、以下の計算方法により算出した金額を地震保険料控除として適用できる。ただし、地震保険料とともに適用する場合には、2つあわせて25,000円が限度額となる。
|
人的控除
| 種類 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者控除 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦・ひとり親控除 |
次にあげる条件すべてに該当し、扶養する子・扶養する親族の有無に応じ適用されます。 1.合計所得金額が500万円以下 2.婚姻していない(配偶者が生死不明の一定の場合を含む) 3.住民票上、事実婚の関係にある人の記載がない
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合には26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者控除 |
本人の合計所得金額により以下の通りになります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者特別控除 |
次の要件を満たす場合に、配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養控除 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎控除 |
合計所得金額に応じ、それぞれ次のとおりとなります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総所得金額等
次の1.と2.の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の1/2の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額となります。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額
次の1.と2.の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の1/2の金額
ただし、総所得金額等で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額となります。
(3)税額控除
1 調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。
1 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のうち少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額
2 合計課税所得金額が200万円を超える場合
次のうち多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
- 5万円
2 配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税所得金額 (種類) |
1,000万円以下の部分 (市民税) |
1,000万円以下の部分 (県民税) |
1,000万円超の部分 (市民税) |
1,000万円超の部分(県民税) |
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当金等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 外貨建等以外の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
3 住宅借入金等特別税額控除
次の1.と2.のいずれか少ない金額を個人市県民税(住民税)から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97,500円または136,500円)
(注意)2.については、入居した年月等の条件により限度額が97,500円または136,500円と異なります。
4 寄附金税額控除
控除額
対象となる寄附金(総所得金額の30%を限度)-2,000円】×税率(市民税6%・県民税4%)
(注意)都道府県・市区町村に対しての2,000円を超える寄附金は、個人市県民税(住民税)の所得割の20%を限度に、特例控除が適用となります。
寄附金のうち2,000円を超える部分が、一定の上限まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
| 控除種類 | 控除方式 | 控除額の計算 |
|---|---|---|
| (1)所得税 | 所得控除 | 寄附金-2,000円 |
| (2)個人住民税 (基本控除) |
税額控除 | (寄附金-2,000円)×10% |
| (3)個人住民税 (特例控除) |
税額控除 | (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) |
(注意)
- 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。
- 個人住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
- (1)の控除対象寄附金は総所得金額等の40%が上限
- (2)の控除対象寄附金は総所得金額等の30%が上限
- (3)の特例控除は、個人住民税所得割の2割が上限。
- 所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される所得税率(0~45%)のうち最大のものを指します。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、寄附をした年の翌年に課税される個人住民税額から控除されます。(ただし、寄附金が(2)または(3)の上限を超える場合は、控除額が少なくなるので注意が必要です。)
5 外国税額控除
所得税で外国税控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除します。
6 税額調整額
所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置です。
調整額の計算
1.扶養親族がいない場合
35万円-(総所得金額等-算出税額)
2.扶養親族がいる場合
35万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+32万円-(総所得金額等-算出税額)
(4)配当割額、株式等譲渡所得割額控除
上場株式配当所得、上場株式等譲渡所得から配当割、株式等譲渡所得割が徴収されている人がその所得について申告した場合、翌年度の個人市県民税から配当割、株式等譲渡所得割を控除します。
なお、控除しきれなかった額がある場合は、合計税額(均等割額含む。)の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





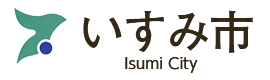
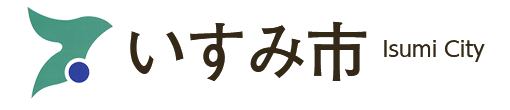





更新日:2024年08月02日