税金の納付が遅れた場合
督促状・催告書
納期限までに納付が確認できない場合、約1か月後に督促状を送付します。督促状の送付は法律で定められています。
督促状を発送しても納付が確認できない場合、催告書の送付や滞納処分等を行っております。
納税相談
病気・失業等の特別な事情があり、納付が困難な方はお早めにご相談ください。ご事情を伺ったうえで、納税の猶予、市税の減免等を含め、納付方法についてご相談をお受けします。
なお、再三の納付催告に対しご連絡等がない場合は税の公平性を保つため財産の差押えを行います。
延滞金
納期限を過ぎてから市税等を納付すると、納期限までに納付した人との公平性を保つため遅れた日数と税額に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金は、次の計算式により算定されます。
延滞金=税額×延滞した日数×延滞金の割合(利率)÷365日
延滞金の割合(利率)の推移
| 期間 | 1.納期限後 1か月以内 |
2.納期限 1か月経過後 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日~令和8年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
| 平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
| 平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
| 平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
| 平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
| 平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
延滞金の割合(利率)について
令和3年1月1日以後
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、表1 1.の割合が適用されます。
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、表1 2.の割合が適用されます。
延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
平成26年1月1日~令和2年12月31日まで
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、表1 1.の割合が適用されます。
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、表1 2.の割合が適用されます。
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
平成25年12月31日以前
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、表1 1.のとおりとなります。 - 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。
滞納処分
滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、その人の財産(不動産、動産、給料、預金など)を差し押えたうえで換価し、滞納している税金に充当する一連の手続きのことをいいます。
法律では、督促状を発送した日から数えて10日を経過した日までに納付がない場合、「差し押えなければならない」と規定されています。
差押を解除するには、対象となった市税等及び納付日までの延滞金を、全て納付することが必要です。
不動産
- 不動産の登記簿上に差押の登記がされます。
- 売買等の財産処分が制限され、任意に売却することが困難になります。
- その後も納付がない場合は、公売により換価し、市税等に充当されます。
預貯金、給与、年金
- 預貯金の場合は金融機関、給与の場合は勤務先、年金の場合は支払者に対して差し押えをします。
- 預貯金の場合は、全額又は滞納額を、給与・年金の場合は法律に基づく差し押え禁止額を除いた金額を支払者から毎月取り立てて、市税等に充当します。
生命保険
- 生命保険契約を解約し、解約返戻金を市税等に充当します。
売掛金
- 事業主などに対して、売掛金・請負代金などを差し押えます。
- 差し押えた売掛金・請負代金などを支払者から取り立てて、市税等に充当します。
動産
貴金属、絵画、古銭、カメラ、自動車などの金銭的価値があり換価処分により市税等に充てることが可能なものすべてが対象となります。捜索により財産を差し押え(占有)し、インターネットオークション等で売却後、市税等に充当します。
滞納処分の流れ
市税等を納期限までに納付されない場合
1.督促
法律の規定により納期限の約1か月後に督促状を発送します。
2.催告
自主納付を促すため催告書を発送します。
3.財産調査及び捜索
財産(預貯金・給与・不動産等)を発見するために、金融機関・勤務先・取引先等に対し調査を行います。
また、財産の発見や差し押えなどのために、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。
(注意)これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができます。(国税徴収法第141条、第142条~第147条)
4.差押
調査により差し押えが可能な財産があった場合は、差押を執行します。
5.換価・公売
差し押えた財産の取り立てまたは公売を実施し、現金化を行います。
6.滞納市税等へ充当
換価した財産を滞納市税等へ充当します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





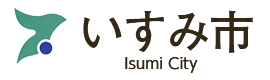
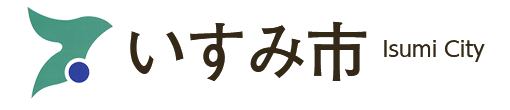





更新日:2026年01月01日