自主防災組織とは
自主防災組織の必要性
初めに地震についてですが、我が国は、世界でも有数の地震国で、過去において大正12年の関東大震災をはじめ数々の大地震に見舞われております。平成7年1月17日未明、兵庫県南部を襲った(阪神・淡路大震災)震度7の激震は、死者6,430名余の尊い生命と財産を奪い去りました。
また、平成19年7月16日午前10時16分に発生した新潟県中越沖地震は、震度6強の激震により、死者15名、重傷者2,316名、住家被害41,803棟の被害となりました。
いすみ市においても駿河湾を震源とする東海地震、相模湾、房総沖を震源とする南関東地震、そして東京や千葉県内の真下で起こる、いわゆる直下型地震などが、今すぐ発生しても不思議ではないといわれております。さらに、都市化の進展に伴い地震による被害も、ますます複雑・多様化してきており、新しい型の災害の発生が心配されています。
つづいて風水害についてですが、日本は、毎年、台風や豪雨に襲われます。昭和26年以降、台風発生数の最多は39個(昭和42年)、最小は16個(平成10年)です。平成12年までの30年間を見ると、1年間に平均約27個発生し、そのうち約3個が日本に上陸しています。
平成16年には、過去最多の10個の台風が日本列島に上陸し、各地に甚大な風水害や土砂災害をもたらしました。
いすみ市においても、近年では平成16年の台風22号、平成19年の台風4号では、土砂災害や洪水により家屋の倒壊や家屋の床上・床下浸水が発生しました。幸いにも人的被害はありませんでしたが、多大な被害が発生しました。
私達は、地震や風水害の発生そのものを防ぐことは出来ませんが、被害を最小限にくい止めることは十分可能なことです。そのために、市をはじめとする防災関係機関が、ふだんから機能強化を図り、その役割を十分に果たさなければならないことはいうまでもありませんが、それにもまして大切なことは、市民の皆さん一人ひとりが「地震」や「風水害」を正しく理解し、いざという時に落ちついた行動がとれるよう、日頃から災害に対する備えを心がけ、隣近所が、助け合える住民の自主的な協力体制が必要です。そして、市や防災関係機関と住民が一体となって総合的な防災体制を確立しておくことが重要なことだと考えております。
自主防災組織とは
一度、大地震が発生すると、火災の同時多発、道路の亀裂、水道管やガス管の破損等の悪条件が重なり、防災関係機関の消火活動、救出・救護活動が、分散、阻害され、十分な機能を果たせなくなることが予想されます。
また、風水害が発生した場合でも土砂災害や洪水により、道路が遮断され、防災関係機関の機能が発揮できないことも考えられます。
このような事態においては、何よりも住民のみなさんの自主的な防災活動、すなわち出火防止、初期消火、救出救護、避難等を行うことが必要不可欠になります。
また、地域にお住まいの高齢者、障がい者等のいわゆる「要配慮者」に対して誰よりも早く救助の手を差し伸べられるのは地域の方々です。
「私達のまちは、私達で守る」という基本的な考えを、家族、隣近所がお互いに協力しあい、地域が一体となった防災活動を行うための組織…これが、「自主防災組織」です。
自主防災組織の結成
自主防災組織をつくるには、まず、地域の実情により、その組織の規模も変わります。
地域のとらえ方としては、
- 地域のみなさんが、防災活動を行う場合に、おたがいに協力して「私達のまちを守る」という連帯感が生まれる規模であること。
- 日常生活上、地域のみなさんが一体性を有する程度の地域であること。
具体的には、区・自治会の組織の範囲などが、これにふさわしいと考えられます。
組織づくりには、次の点を考慮して下さい。
- 区等に防災部を設置している場合は、その組織の活動内容の充実・強化を図る方向で。
- 区等で、特に防災活動を行っていない場合は、区の活動の一環として防災部を設ける等、組織化を図りましょう。
「防災計画」の作成
大地震や風水害により災害が発生した場合すばやく、能率よく防災活動ができるよう、「自主防災組織」として、あらかじめ、自分達の防災計画を作りましょう。地域の実情に合わせ予想される被害を想定して具体的に決めることが大切です。
留意点
- 効果的な組織作りのためには、各自の任務分担を明確にする。
- 組織を育成し活動していくためには、良きリーダーが必要である。また、そのリーダーを中心に一つにまとまるように、一人ひとりが協力していくことが大切である。
- 地震は、いつ発生するかわかりません。昼と夜とでは、地域内に居住している人が違うので、いろいろな場合を想定して具体的に計画をたてておく。
防災組織編成の例
情報班

情報班は、行政からの情報および指示等を住民に正確に伝達することと、地域の被害状況を防災機関に連絡できるよう訓練を実施します。
また、ビデオやパンフレットなどを用いて防災の啓発を行います。
消火班

可搬式動力ポンプ、消火器、三角バケツなどの消火器具の点検よび使用方法や効果的な消化技術の習得を行うほか住民への取扱方法の指導を行います。
また、地震時の火災は、同時多発することが予想されますので、隣近所が協力し合える体制を作りましょう。
救出救護班
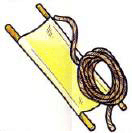
はしご、ロープ、エンジンカッターなど救出用資機材の使用・救出方法に関する知識および技術の習得、負傷者の搬送方法、応急手当の方法の習得のための訓練を行います。
避難誘導班

実際に避難場所まで歩き、避難経路を確認して下さい。少なくても数方向の避難経路を考え、身障者、高齢者、幼児等を最優先して下さい。また、避難路の危険箇所や道幅、距離などの確認が必要です。
給食・給水班

物資の備蓄・管理を行うとともに、米をマキで炊飯するなどの訓練を行います。また、食糧を各人に効率よく配る方法なども考慮しておくとよいでしょう。なお食料・飲料水は、各家庭でも3日分位の非常用飲食料を確保して下さい。
日常の活動
防災の正しい知識を身につけることが大切!
いざというときに、住民のみなさんが、効果的に活動できるかどうかは、日頃、防災に関する正しい知識を持っているかどうかにかかっております。
そのためには、自主防災組織として、あらゆる機会をとらえて、住民のみなさんが、お互いに防災知識を高め合えるよう知識の習得に努めることが大切です。
いざという時に備えて訓練をする
災害が発生したとき、私達の心体はなかなか思うように動かないものです。落ちついた行動がとれるよう防災活動に必要な知識、技術に習熟しておきましょう。
そのために、市が防災意識の向上を図るため、毎年行っている「総合防災訓練」に積極的に参加する。また、市や消防署では、申し込みがあれば、いつでも指導・訓練を住民と一緒に行っていきます。
平成26年度のいすみ市津波避難訓練より

【観光客の避難訓練】

【孤立者救助訓練】

【行方不明者捜索訓練】

【炊き出し訓練】
非常時の活動
情報を早く正確に伝える
災害が発生する恐れがあるときや、発生した場合に的確な予防・応急体制をとるには、正確な情報を迅速に集めて伝達することが必要です。伝達経路として「自主防災組織」の果たす役割は非常に重要です。
初期消火が大切
過去の大地震の教訓として、地震による被害の中で一番恐ろしいのは、火災の同時多発です。
最初の揺れが大きくて火の始末ができなくても地震の揺れは1~2分間といわれておりますから、揺れがおさまってからすばやく火の始末をし、かりに出火した時には「火事だ!」と大声で叫び隣近所の人達の協力をもとめ、消火器、バケツ等で初期消火をいたします。
そして、何よりも「119番」に連絡です。
避難誘導活動
災害が発生し、また発生する恐れがある場合、市では、市民の生命、身体に危険が生じると判断した時は、避難の勧告または、指示を行います。
避難活動は、次のことに注意して行いましょう。
- 避難情報は、地域内のすべての人に正確かつ迅速に伝達すること。
- 避難誘導責任者の指示に従って全員がまとまって行動すること。
- 地域内の身障者・高齢者・幼児を最優先すること。
救出・救護活動
大地震により、負傷者が出た場合これらの人を救出し、救護する必要があります。
留意点
- 資機材を有効に活用するとともに、必要と認められるときは、速やかに消防機関等に出動を要請する。
- 状況に応じて、できるだけ周囲の人から協力を求める。
- 負傷者を救出したり、自分達で応急手当を施し、さらに医師の手当が必要な場合には直ちに消防機関等に出動を要請する。
- 給食給水活動 大規模な災害が発生した場合では、食料品、飲料水、生活用品が不足することが考えられます。そこで各家庭において、3日分位は生活ができる飲食物を用意しておきましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





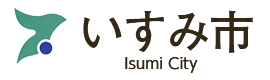
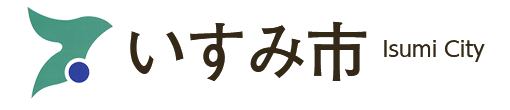





更新日:2022年03月02日